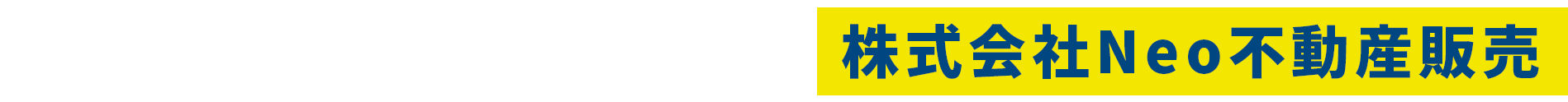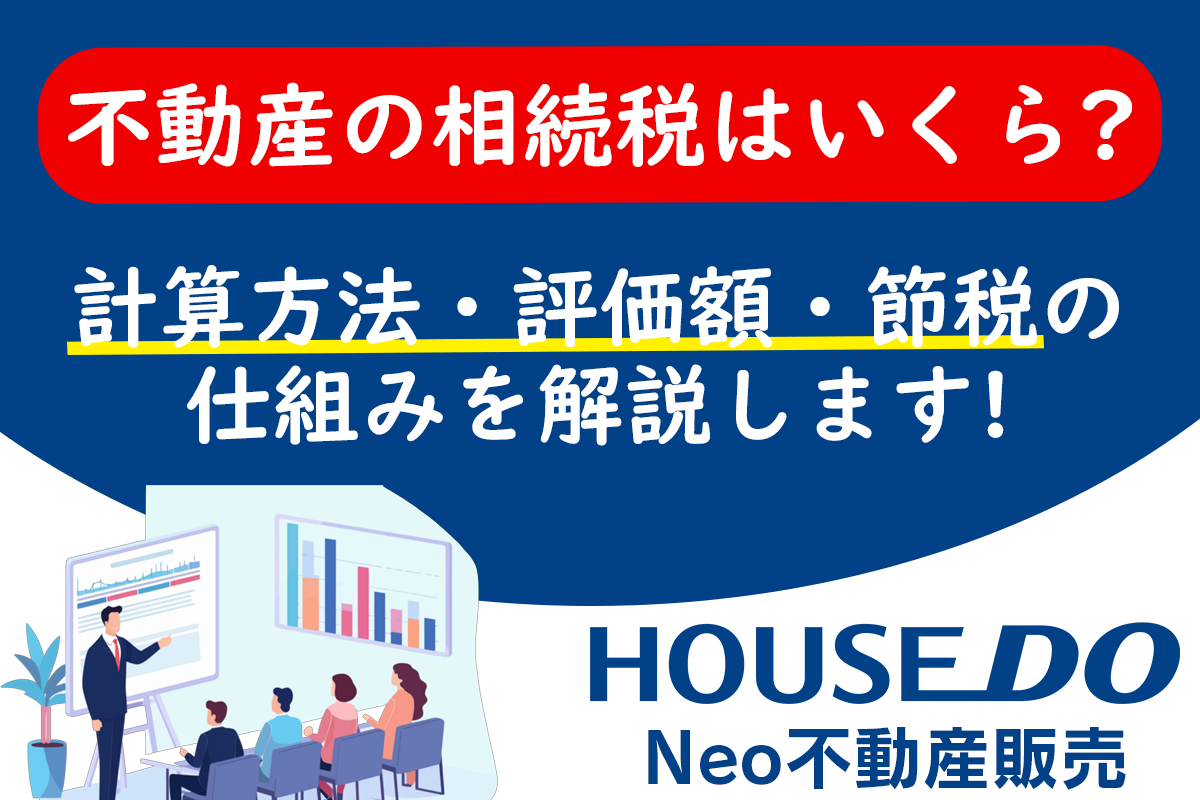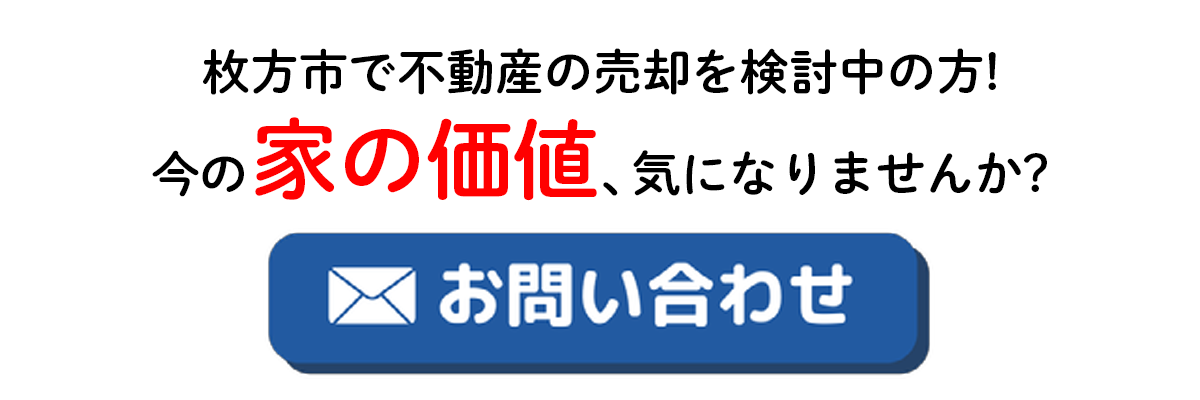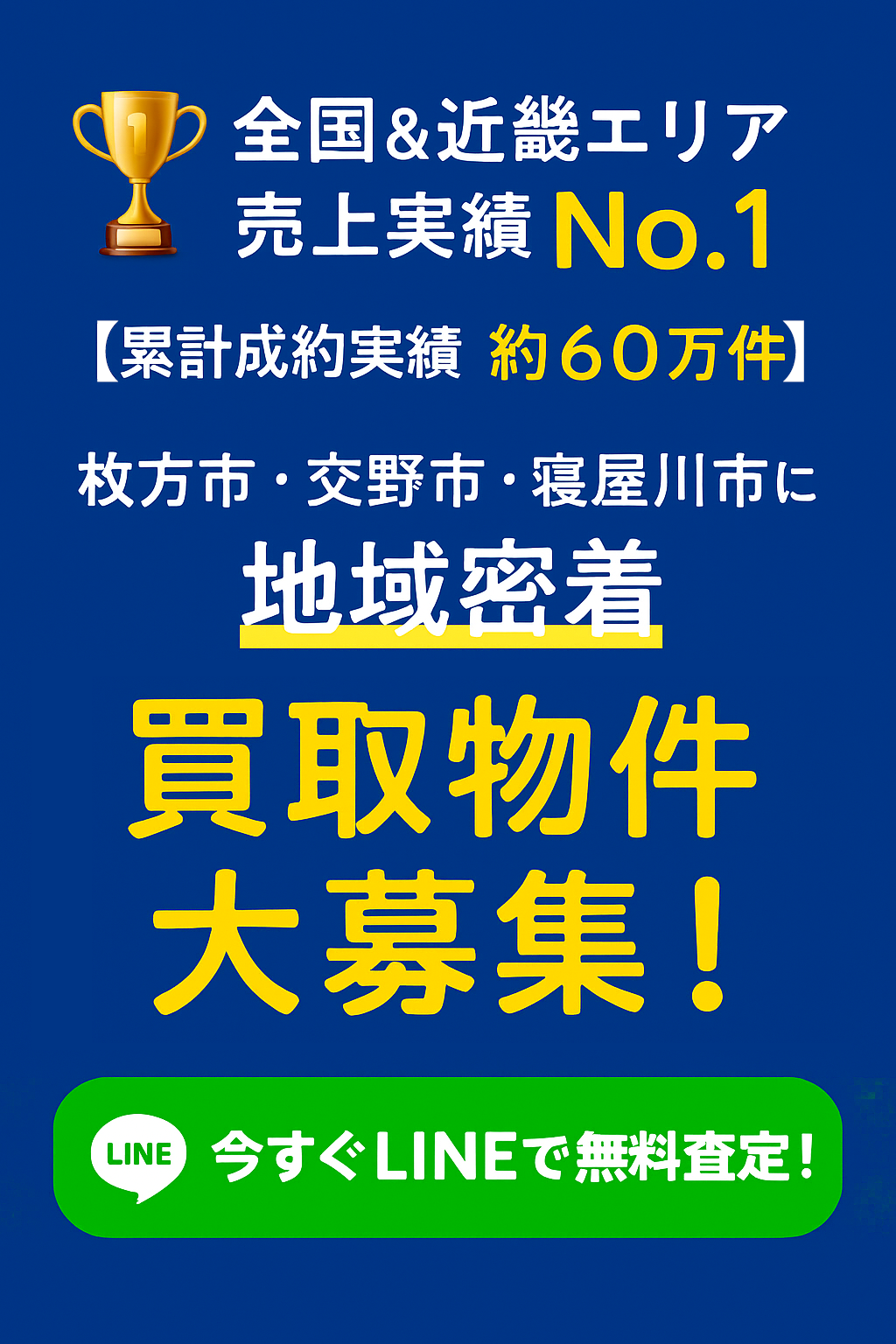不動産の相続税っていくら?
「親の家を相続したら、相続税はいくらかかるの?」──相続が発生した際、誰もが気になるのが税金の金額です。
実は相続税は一律ではなく、財産の総額・相続人数・不動産の評価方法などによって大きく変わります。ここでは、不動産を相続した場合の相続税の計算方法と、節税のポイントをわかりやすく解説します。
相続税の基本構造

相続税は、次のステップで計算されます。
- 遺産の総額を算出する(不動産・預貯金・株式など)
- 「基礎控除額」を差し引く
- 残った金額に応じて税率をかける
- 配偶者・小規模宅地・生命保険などの各種控除を適用
基礎控除の計算式
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、相続人が配偶者と子1人の2人なら、3,000万円+1,200万円=4,200万円が控除されます。
税率の目安
基礎控除後の課税対象額に対し、10〜55%の累進税率が適用されます。
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
不動産の評価方法:時価ではなく「相続税評価額」

不動産を相続する際の評価は、実際の売却価格(時価)ではなく、税務上の「相続税評価額」で行われます。一般的に、時価の約70〜80%程度とされています。
土地の評価方法(路線価・倍率方式)
土地の評価は、国税庁が毎年公表する「路線価」をもとに計算します。路線価とは、主要な道路に面する土地1㎡あたりの価格です。
計算式:評価額 = 路線価 × 土地面積 × 各種補正率
たとえば、路線価が20万円/m²、土地面積が200m²の場合は
20万円 × 200m² = 4,000万円が評価額の目安になります。
※角地・奥行・形状などで補正が入ることもあります。
建物の評価方法
建物は「固定資産税評価額」がそのまま相続税評価になります。固定資産税評価額は建築年数や構造によって変動し、建築後20年以上の木造住宅では評価額がかなり低くなる傾向があります。
貸家・アパートなど賃貸物件の評価
賃貸物件は、入居者がいる分だけ価値が下がると見なされ、貸家建付地や借家権割合(通常30%)によって評価額が20〜30%下がります。これは「収益還元法」に基づく考え方で、節税に有利な形態です。
次章では、これらの評価額を使って実際にどのように税額を計算するのか、シミュレーション形式で詳しく見ていきましょう。
相続税の計算ステップを実例で解説

ここでは、不動産を含む遺産総額の具体例を使って、実際の相続税をシミュレーションしてみましょう。
【モデルケースA】相続人2名(配偶者・子1)/自宅+預金
- 自宅(土地+建物)の相続税評価額:4,000万円
- 預貯金:2,000万円
- その他財産:なし
- 相続人:配偶者と子1人
① 遺産総額
4,000万円+2,000万円=6,000万円
② 基礎控除の計算
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
③ 課税対象額
6,000万円−4,200万円=1,800万円
④ 法定相続分で按分
配偶者:1/2 → 900万円/子:1/2 → 900万円
⑤ 税率をかける
| 法定相続分ごとの課税価格 | 税率 | 控除額 | 算出税額 |
|---|---|---|---|
| 900万円 | 10% | 0円 | 90万円 |
算出税額合計=配偶者90万円+子90万円=180万円
この金額から、配偶者の税額軽減が適用され、配偶者分はほぼ非課税となります。
最終的な納税額=およそ子の分の90万円が目安です。
【モデルケースB】相続人3名(子3人)/土地・アパート・現金
- 土地(路線価評価):6,000万円
- 賃貸アパート:3,000万円
- 現金:2,000万円
- 相続人:子3人
① 遺産総額
6,000+3,000+2,000=1億1,000万円
② 基礎控除
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
③ 課税対象額
1億1,000万円−4,800万円=6,200万円
④ 法定相続分で按分(子3人均等)
6,200万円÷3=1人あたり2,066万円
⑤ 税率を適用
2,066万円 → 税率15%、控除50万円
算出税額 = 2,066万円 × 15% − 50万円 = 約260万円
⑥ 各種特例を適用
このケースでは、アパートや貸家部分に「貸家建付地」「借家権割合」の評価減があり、実際には評価額が20〜30%下がる可能性があります。結果として税額は200万円前後まで圧縮できる場合があります。
「小規模宅地等の特例」でさらに税額を減らす
被相続人が住んでいた自宅や事業用地は、一定の条件を満たすと最大80%の評価減が受けられます。これは相続税対策で最も効果が高い制度の一つです。
対象の宅地と減額割合
| 区分 | 上限面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地(自宅) | 330㎡まで | 80% |
| 特定事業用宅地 | 400㎡まで | 80% |
| 貸付事業用宅地 | 200㎡まで | 50% |
たとえば、路線価評価6,000万円の土地が自宅であり、相続人が同居している場合、80%減が適用されると評価額は1,200万円になります。これだけで税額が数百万円減る計算です。
「家なき子特例」にも注目
同居していなかった子でも、自身が持ち家を所有していなければ「家なき子特例」で同様の80%減を受けられるケースがあります。
ただし、過去に持ち家を売却した場合や配偶者が持ち家を所有している場合は対象外になるため、専門家への確認が必要です。
次の章では、相続税を支払うための資金準備方法や、売却・延納・物納といった選択肢について詳しく見ていきます。
相続税の納税資金をどう準備するか?

相続税の申告・納税期限は、相続開始(死亡)から10か月以内です。
この期間内に遺産分割を済ませ、申告書を提出し、現金で納税する必要があります。
しかし、遺産の多くが不動産の場合、現金が不足して納税に困るケースも少なくありません。
① 不動産を売却して納税資金を確保
最も一般的な方法が「相続不動産の売却」です。
特に自宅や空き家を相続した場合、使用予定がないなら早期に売却することで、納税資金を確保できます。
このとき、売却益に課税される「譲渡所得税」も考慮が必要ですが、要件を満たせば空き家3,000万円特別控除を適用できる可能性があります。
たとえば、相続した家を相続から3年以内に売却すれば、最大3,000万円を控除できるため、税金を大きく抑えることができます。
② 延納(分割払い)制度
すぐに現金を用意できない場合、一定の条件を満たせば「延納制度」が利用可能です。
延納とは、相続税を年賦で分割して支払う方法で、5〜20年の分割払いが認められています。
ただし、利子税(年0.9〜6%程度)が課されるため、長期延納は総支払額が増える点に注意しましょう。
③ 物納制度(不動産などで納税)
延納でも支払いが困難な場合は、「物納」として不動産や株式で納税する方法もあります。
ただし、国が受け取る財産として適格である必要があり、土地の境界や評価が曖昧な場合は認められません。
不動産を物納する場合は、税務署の審査に時間がかかるため、早めの準備が必要です。
相続登記義務化と名義変更の注意点

2024年4月から、相続登記が義務化されました。
不動産を相続したら、取得を知ってから3年以内に登記申請を行う必要があります。
これを怠ると10万円以下の過料(罰金)が科されることも。
登記が完了していないと、売却・担保設定・物納のすべてが進められません。
相続登記の流れ:
- 被相続人の戸籍・除籍・住民票の収集
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成と全員の実印押印
- 登記申請(法務局)→ 登記完了通知を受領
司法書士に依頼すれば、手間を省きながらスムーズに完了できます。
相続税の申告期限(10か月)と登記義務(3年)を混同しないよう注意しましょう。
不動産の相続税を抑える3つのポイント
- ① 評価額を正しく見直す
不整形地・高低差・私道負担などの補正で評価額を下げられることがあります。 - ② 小規模宅地等の特例を活用する
自宅や事業用地なら、最大80%の減額が可能。条件を満たすように事前整理を。 - ③ 生前贈与や土地活用も検討する
早めの生前対策として、「相続時精算課税制度」や「賃貸併用住宅の建築」で評価を圧縮できます。
よくある質問(FAQ)

- Q. 固定資産税評価額=相続税評価額ですか?
A. いいえ。固定資産税評価額は市町村が算出するもので、相続税評価額は国税庁が定める路線価や倍率をもとに計算します。通常、相続税評価額は固定資産税評価額の1.1倍前後です。 - Q. 相続税の申告は誰がやる?
A. 相続人代表が申告しますが、税理士に依頼するのが一般的です。特に不動産を含む場合、評価方法が複雑なため専門家のサポートが不可欠です。 - Q. 不動産を相続しても、現金がないと困りますか?
A. はい。不動産は流動性が低いため、納税資金を準備できないケースも多いです。早期の売却や延納・物納の選択肢を検討しましょう。
まとめ:不動産の相続税は「評価×特例×期限管理」で変わる
不動産の相続税は、評価額の算定方法や控除の適用で大きく差が出ます。
まずはおおまかな評価額を把握し、基礎控除・小規模宅地・配偶者軽減などの特例を適用できるかを確認しましょう。
ハウスドゥ 京阪くずは店では、相続不動産の査定・税理士連携・売却支援までワンストップで対応しています。
相続税が「いくらかかるのか」を把握したい方や、売却による節税を検討している方は、ぜひお気軽にご相談ください。
▶ 無料相談・査定はこちら:
https://neo-baikyaku-pro.jp/contact/
相続税対策は「知っているかどうか」で結果が変わります。
まずは今ある不動産の評価を確認し、早めに備えましょう。