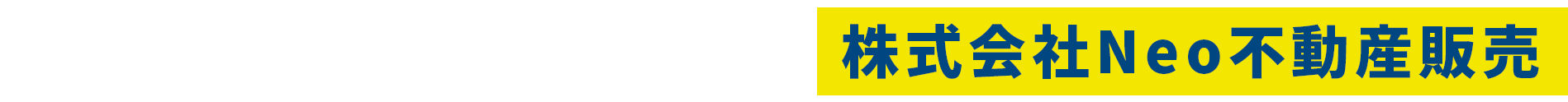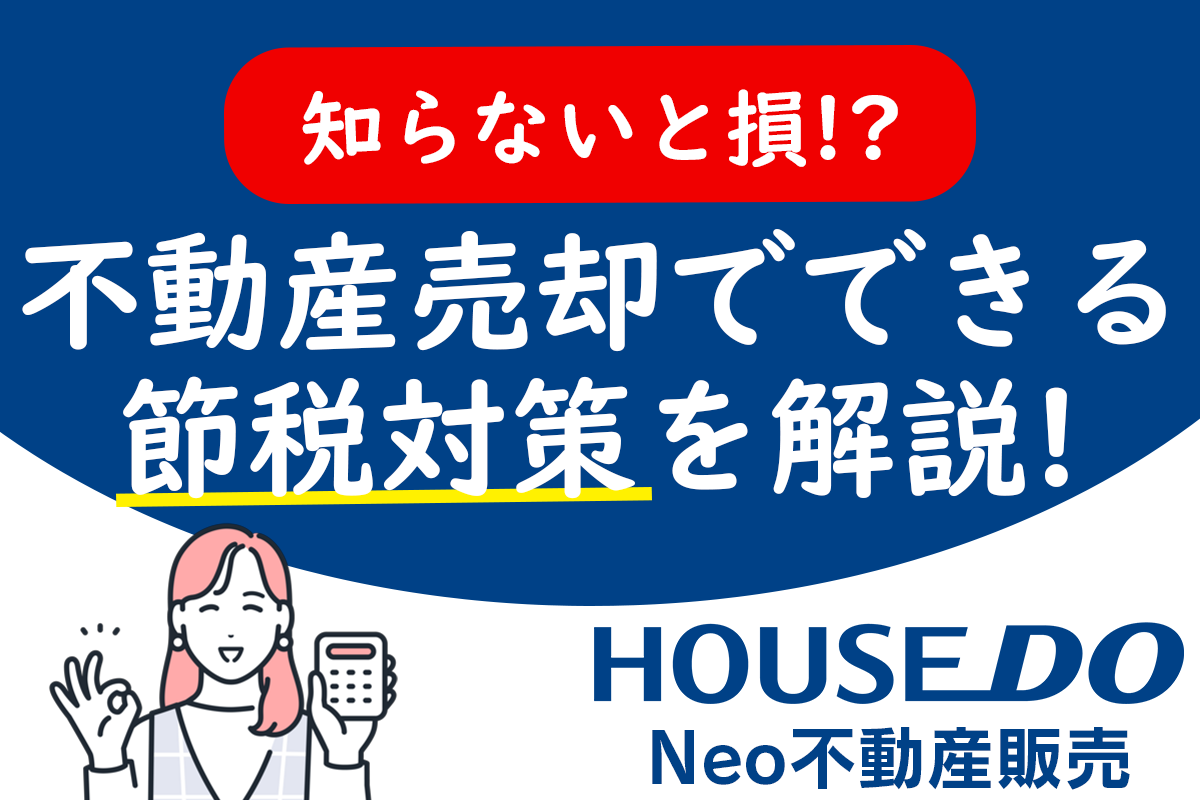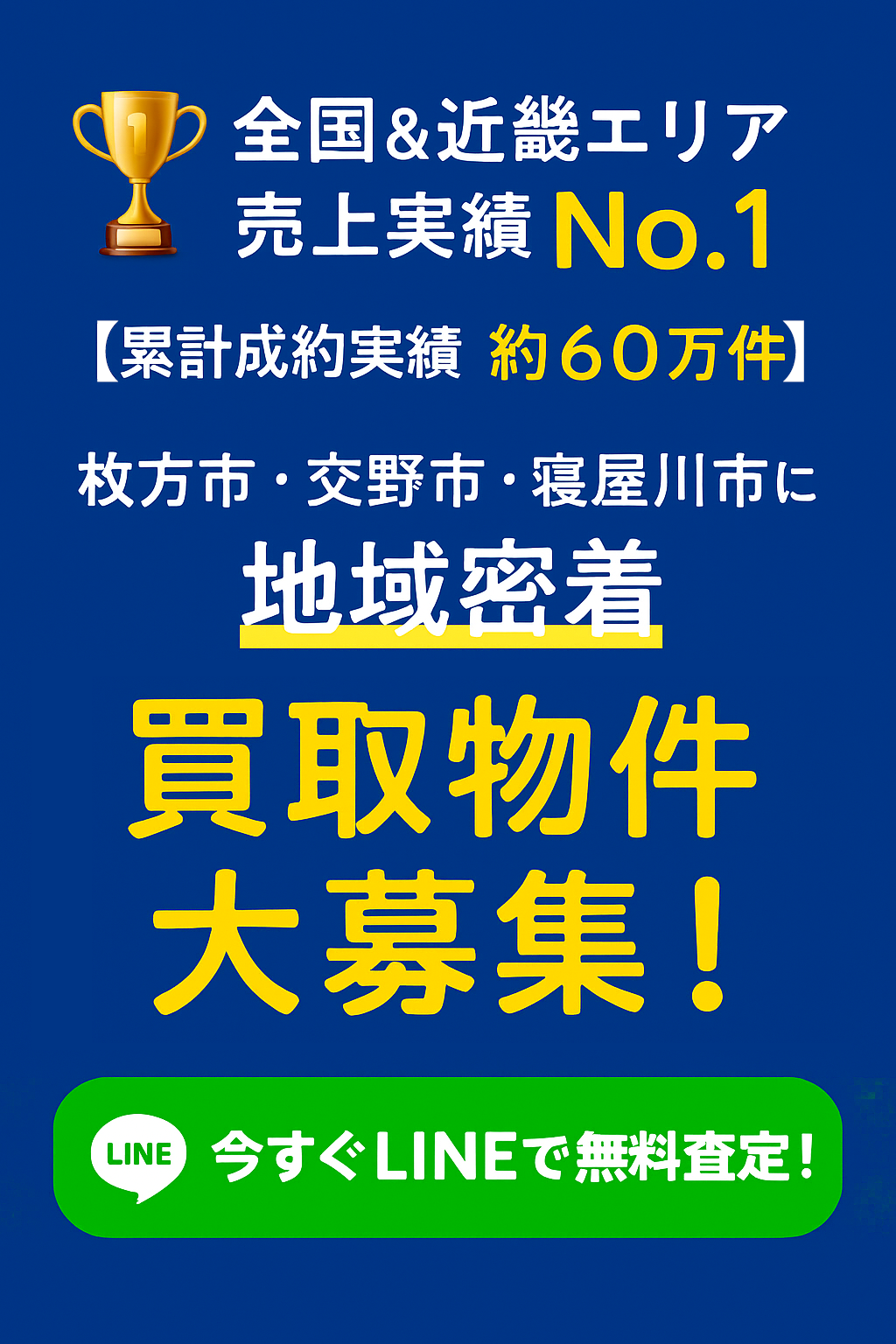不動産売却にかかる税金の基本

不動産を売却すると、その売却益に対して税金が発生します。多くの方は「売却金額がそのまま手元に残る」と考えがちですが、実際には税金や諸費用が差し引かれるため、思っていたより少なくなるケースも少なくありません。
不動産売却に関して代表的にかかる税金は以下の3つです。
- 譲渡所得税(所得税+住民税+復興特別所得税)
- 印紙税(売買契約書に貼る収入印紙)
- 登録免許税(抵当権抹消登記・相続登記などの際に必要)
譲渡所得税の仕組み
不動産売却で最も大きな負担になるのが「譲渡所得税」です。これは、不動産を売った利益に課税される税金で、次のように計算されます。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
- 取得費:購入代金や建築費、購入時の諸費用など
- 譲渡費用:仲介手数料、印紙代、測量費など売却にかかった費用
この譲渡所得に対して税率がかかりますが、所有期間によって税率が大きく変わります。
| 所有期間 | 課税区分 | 税率(所得税+住民税) |
|---|---|---|
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 約39% |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 約20% |
例えば、500万円の譲渡所得が発生した場合、短期譲渡では約195万円の税金がかかりますが、長期譲渡では約100万円で済みます。所有期間による差は非常に大きく、節税を考える上で重要なポイントになります。
その他の税金
印紙税は売買契約書に貼る収入印紙代で、契約額によって金額が決まります。2,000万〜5,000万円の契約であれば1万円程度が目安です。
また、住宅ローンを完済する際に必要な抵当権抹消登記や、相続した不動産を売る場合には相続登記が必要となり、登録免許税と司法書士報酬がかかります。これらは数万円〜十数万円程度が一般的です。
節税につながる控除・特例制度

不動産売却において最大のポイントは「控除や特例をどれだけ活用できるか」です。知らずに手続きを進めると、本来は減らせるはずの税金をそのまま支払うことになり、大きな損につながります。ここでは代表的な制度をご紹介します。
3,000万円特別控除
居住用の不動産を売却した場合、最大3,000万円までの譲渡所得を控除できる制度です。これにより、多くのケースで課税所得がゼロになる可能性があります。
例: 譲渡所得が2,500万円の場合 → 3,000万円控除を使えば課税所得はゼロ。結果、譲渡所得税がかからない。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 売却する不動産が本人の居住用であること
- 売却前に居住していた期間があること
- 家族や親族への売却ではないこと
特定居住用財産の買換え特例
マイホームを売却して新しい家を購入する場合、譲渡益にかかる税金を将来に繰り延べることができる制度です。
「税金がゼロになる」わけではありませんが、次に売却する際まで課税を先送りできるため、大きな資金負担の軽減になります。
10年超所有軽減税率の特例
マイホームを10年以上所有している場合に使える優遇措置です。通常の長期譲渡所得の税率(20%)よりも低い税率で課税されます。
| 課税譲渡所得金額 | 税率(所得税+住民税) |
|---|---|
| 6,000万円以下 | 14.21% |
| 6,000万円超 | 20.315% |
相続不動産の特例(空き家の3,000万円控除)
相続で取得した空き家を売却する場合にも、特別控除が使えるケースがあります。一定の耐震基準を満たすリフォームや取り壊しをした上で売却すれば、譲渡所得から3,000万円まで控除可能です。
枚方市でも「親から相続した実家を空き家のまま放置するのはもったいない」と売却を選ぶ方が増えており、この特例をうまく活用すれば税負担を大幅に減らすことができます。
控除や特例を使う際の注意点
- 同じ年に複数の特例を併用できない場合がある
- 確定申告をしなければ控除を受けられない
- 制度には適用期限や要件があるため、事前確認が必要
控除や特例は「知っているかどうか」で税額が大きく変わります。必ず専門家に確認し、自分に合った制度を最大限に活用することが重要です。
譲渡所得の計算方法と節税の工夫

不動産を売却すると「売却代金=手取り」ではなく、譲渡所得をもとに税金が課されます。正しい計算方法を理解することが、節税への第一歩です。
譲渡所得の基本計算式
譲渡所得は以下の式で計算されます。
譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)
- 譲渡価額: 実際に不動産を売却した価格
- 取得費: 不動産を購入した際の代金、建築費、購入時の諸費用など
- 譲渡費用: 売却にかかった仲介手数料、登記費用、測量費など
この譲渡所得に対して、所有期間に応じた税率がかかります。
所有期間による税率の違い
| 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5年以下(短期譲渡) | 30% | 9% | 39% |
| 5年超(長期譲渡) | 15% | 5% | 20% |
例えば同じ1,000万円の利益でも、短期譲渡なら390万円、長期譲渡なら200万円と、税額が大きく変わります。
取得費を正しく計上することが節税の鍵
譲渡所得を減らすには「取得費」をできるだけ正確に計上することが重要です。取得費を過少に申告してしまうと、結果的に課税所得が大きくなり、税額が増えてしまいます。
取得費に含められるものの例:
- 購入時の仲介手数料
- 登記費用、登録免許税
- 不動産取得税
- 建築費用や増改築費用
- 測量費用
譲渡費用も忘れずに計上
売却時にかかった費用も譲渡所得から差し引けます。代表的なものは以下の通りです。
- 仲介手数料
- 測量費用
- 建物の取り壊し費用
- 司法書士や弁護士への報酬
節税の工夫
譲渡所得を少なく見積もるためには、領収書や契約書を保管しておくことが欠かせません。特に古い不動産の場合、取得費が分からないと「概算取得費(譲渡価額の5%)」で計算され、税金が増えてしまうケースがあります。
また、売却前に耐震リフォームや取り壊しをして空き家特例を使うなど、制度と組み合わせれば大幅な節税につながります。
節税対策のためにやってはいけない落とし穴

不動産売却では節税が大きなテーマになりますが、「節税のためにやったつもりが逆効果」になるケースも少なくありません。ここでは特に注意すべき落とし穴を紹介します。
① 贈与で名義変更してから売却する
「親の名義だと税金が高そうだから、先に子どもに贈与してから売却しよう」と考える方がいます。しかし、この方法は高額な贈与税が発生し、かえって大きな負担になります。
- 贈与税は相続税よりも税率が高い
- 基礎控除は年間110万円と少ない
- 安易な名義変更で数百万円の贈与税を課されることもある
「節税になる」と思ってやったことが、結果的に税負担を増やす典型例です。
② 節税制度を誤解して使えないケース
代表的なのが「居住用財産の3,000万円特別控除」です。条件を満たしていないのに申告しても適用されず、あとで追徴課税されることがあります。
- 住んでいない家(投資用マンションなど)は対象外
- 親子間・同族会社への売却は対象外
- 過去2年間に同じ控除を使っていると適用不可
「知らなかった」では済まされないため、制度の条件は必ず事前に確認する必要があります。
③ 節税だけにとらわれて損をする
節税を優先するあまり、タイミングを逃して結果的に売却価格が下がることもあります。
例えば、「軽減税率を使うために10年を待つ」としても、その間に不動産の価値が大幅に下がってしまえば本末転倒です。節税額以上に売却益が減ってしまうリスクがあります。
④ 確定申告を忘れて控除を受けられない
不動産売却における節税制度は、確定申告をしないと適用されません。会社員の方で「申告は不要だと思っていた」という理由で控除を受けられず、余計な税金を支払ってしまうケースが実際にあります。
特に「居住用財産の3,000万円控除」や「空き家特例」などは、自動的に適用されるわけではありません。必要書類を揃えて正しく申告することが必須です。
⑤ 相続との関係を考えずに売却する
相続税対策を考えずに売却してしまうと、将来的に子どもや相続人に大きな税負担がかかることがあります。
- 相続税の基礎控除や小規模宅地の特例を見落とす
- 相続時精算課税制度を安易に選択してしまう
- 生前贈与と売却を混同して、損をしてしまう
売却と相続は切り離して考えられないため、両方の制度を踏まえて検討する必要があります。
節税対策を成功させるための手順

不動産売却で節税を成功させるには、場当たり的に制度を使うのではなく、計画的に準備を進めることが大切です。ここでは具体的な手順を紹介します。
① 不動産の評価額を把握する
まず最初にやるべきことは、売却予定の不動産がどれくらいの評価額になるのかを確認することです。
- 固定資産税評価額(市区町村の課税根拠となる金額)
- 路線価(国税庁が定める相続税・贈与税の基準価格)
- 市場価格(不動産会社が査定する実際の売却価格)
これらを整理することで、譲渡所得のシミュレーションができ、どの制度を活用すべきかの判断材料になります。
② 節税制度の適用可否を確認する
自分のケースで使える節税制度を整理します。代表的なものは以下のとおりです。
| 制度名 | 内容 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 居住用財産の3,000万円特別控除 | マイホーム売却の譲渡所得から3,000万円控除 | 自分や家族が住んでいた住宅であること |
| 所有期間10年超の軽減税率 | 譲渡所得税が14%に軽減 | 10年以上所有し、かつ居住用財産であること |
| 空き家特例(3,000万円控除) | 相続で得た空き家を売却した際に特別控除 | 昭和56年5月31日以前建築、耐震改修または取壊し条件あり |
| 買換え特例 | 売却益を次の住宅に充当すれば課税繰延べ | 一定期間内に新居を取得すること |
制度は併用できない場合が多いため、どれを優先するかを整理することが重要です。
③ 専門家に相談する
不動産売却の節税は複雑で、自分だけで判断すると誤りや漏れが出やすいです。
- 不動産会社:市場価格や売却戦略を提案
- 税理士:譲渡所得税・相続税のシミュレーション
- 司法書士:登記や相続に関する手続きを代行
これらの専門家と連携して進めることで、リスクを最小限に抑えながら節税効果を最大化できます。
④ 売却時期と所有期間を調整する
不動産売却は「いつ売るか」で税額が大きく変わります。
- 所有期間5年を超えると税率が39%→20%に下がる
- 所有期間10年を超えると軽減税率の対象になる
- 評価額が見直されるタイミングで贈与・相続を検討する
節税効果を狙うなら、売却のタイミングも戦略的に選ぶ必要があります。
⑤ 確定申告を正しく行う
最後に、節税効果を確実に得るためには確定申告が欠かせません。
- 譲渡所得の計算書類(売買契約書・領収書)
- 控除適用に必要な証明書(住民票、登記事項証明書など)
- 税理士によるチェックを受けると安心
これらを準備して期日までに申告すれば、余分な税金を払わずに済みます。
まとめと実践的アドバイス

ここまで、不動産売却における節税対策の基本から実践方法まで解説しました。ポイントを改めて整理すると次の通りです。
不動産売却の節税ポイント
- 不動産売却には譲渡所得税がかかり、所有期間や条件で税率が大きく変わる
- 3,000万円特別控除や空き家特例など、税金を軽減できる制度がある
- 制度の適用には要件や期限があり、正しく理解しておくことが必要
- 売却時期や所有期間を調整することで大きな節税効果が得られる
- 確定申告を正しく行うことで控除や特例を活用できる
実践的なアドバイス
実際に不動産を売却する際には、以下の流れを意識するとスムーズです。
- まずは固定資産評価額や市場価格を調べ、譲渡所得をシミュレーション
- 適用できる控除や特例を確認し、節税効果を把握
- 専門家(税理士・不動産会社・司法書士)に相談して最適な方法を検討
- 売却のタイミングを戦略的に選び、所有期間を有利に活かす
- 確定申告を忘れず、必要書類を準備して期限内に申告する
地域特性を踏まえた売却
たとえば枚方市のように京阪沿線の駅近エリアでは需要が高く、売却価格も安定しやすい傾向があります。一方で郊外や築古物件でも、買取制度やリフォーム提案を活用すれば売却可能です。地域事情に精通した不動産会社に相談することで、節税と高値売却の両立が可能になります。
さいごに
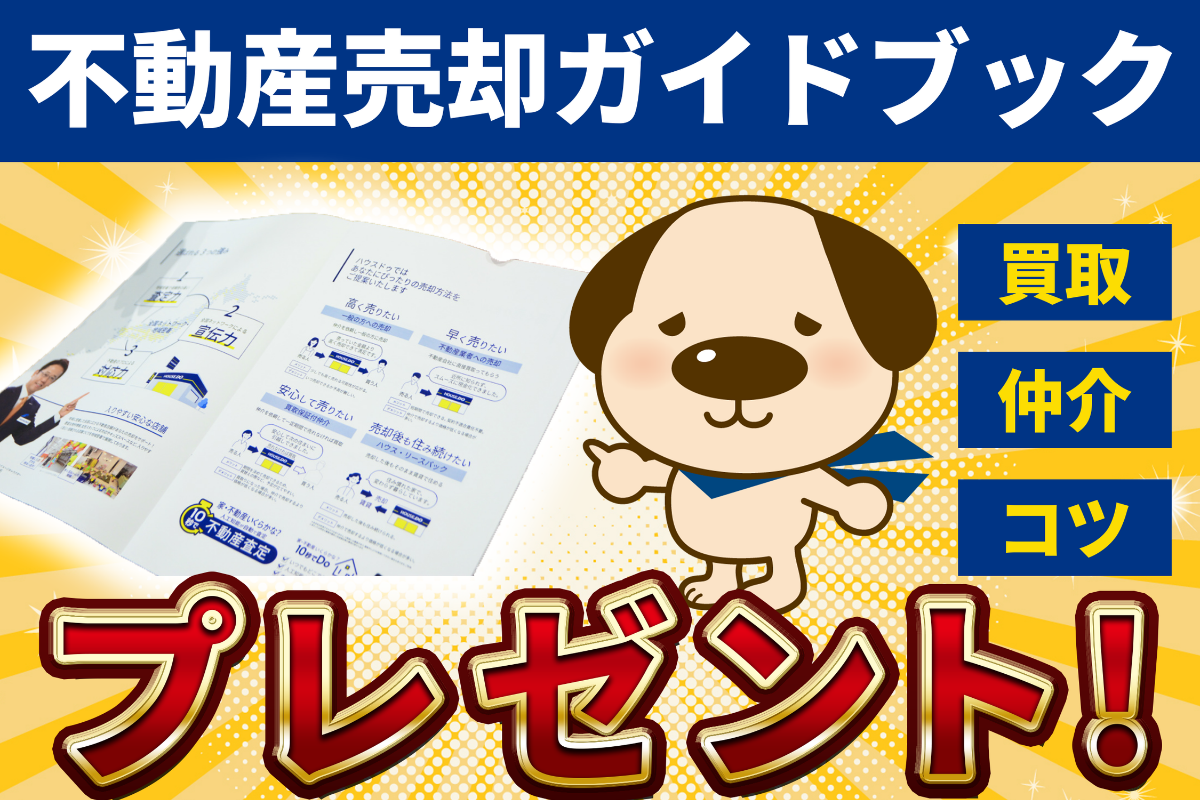
不動産売却は「売って終わり」ではなく、税金対策を含めた計画が不可欠です。節税を意識せずに売却すると数百万円単位で損をすることもありますが、制度を正しく活用すれば負担を最小限に抑えられます。
ハウスドゥ 京阪くずは店では、不動産売却から相続・税金相談までトータルでサポートしています。これから売却を検討している方や「自分の場合どれくらい税金がかかるのか知りたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。公式LINEかメールでのお問い合わせで『不動産売却・相続ガイドブック』を無料でプレゼント中です。
公式LINE、お問い合わせフォームなら24時間受付していますのでお気軽にお問い合わせください。