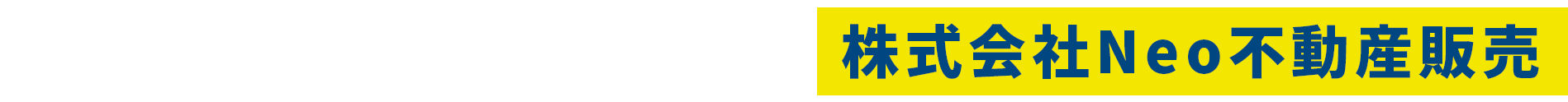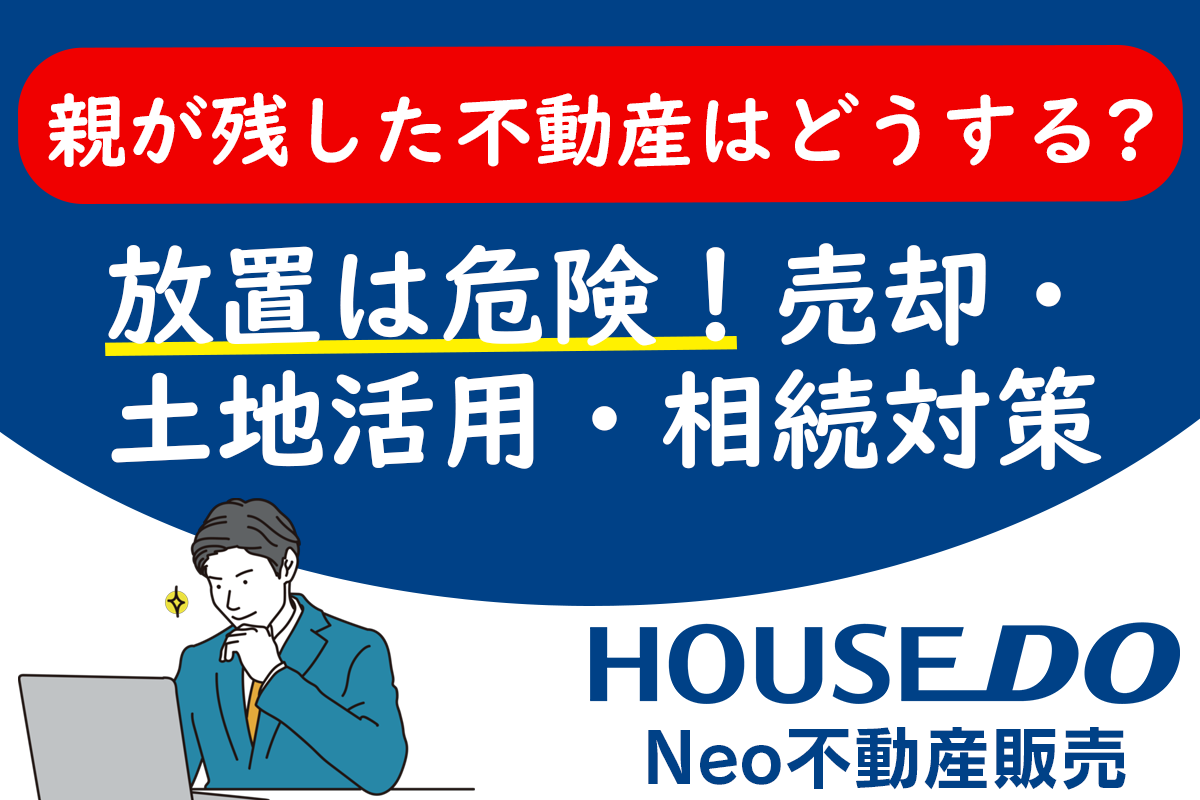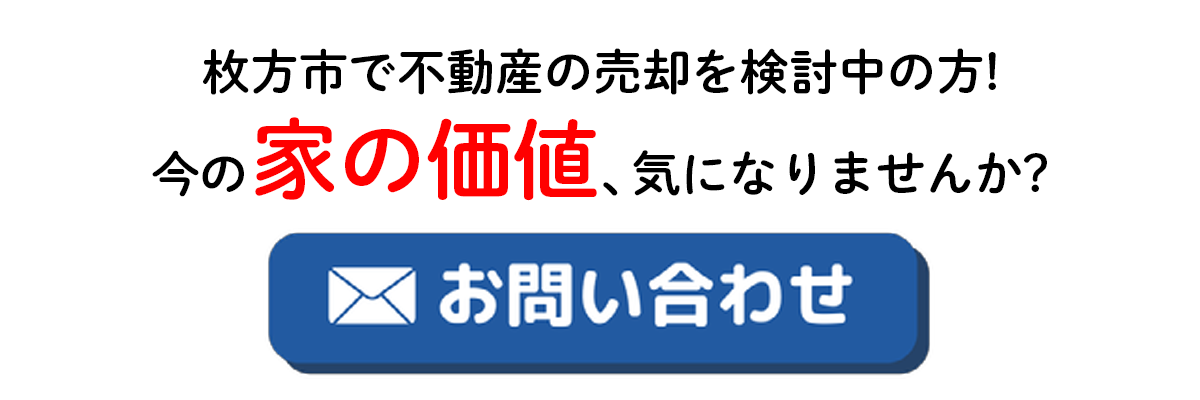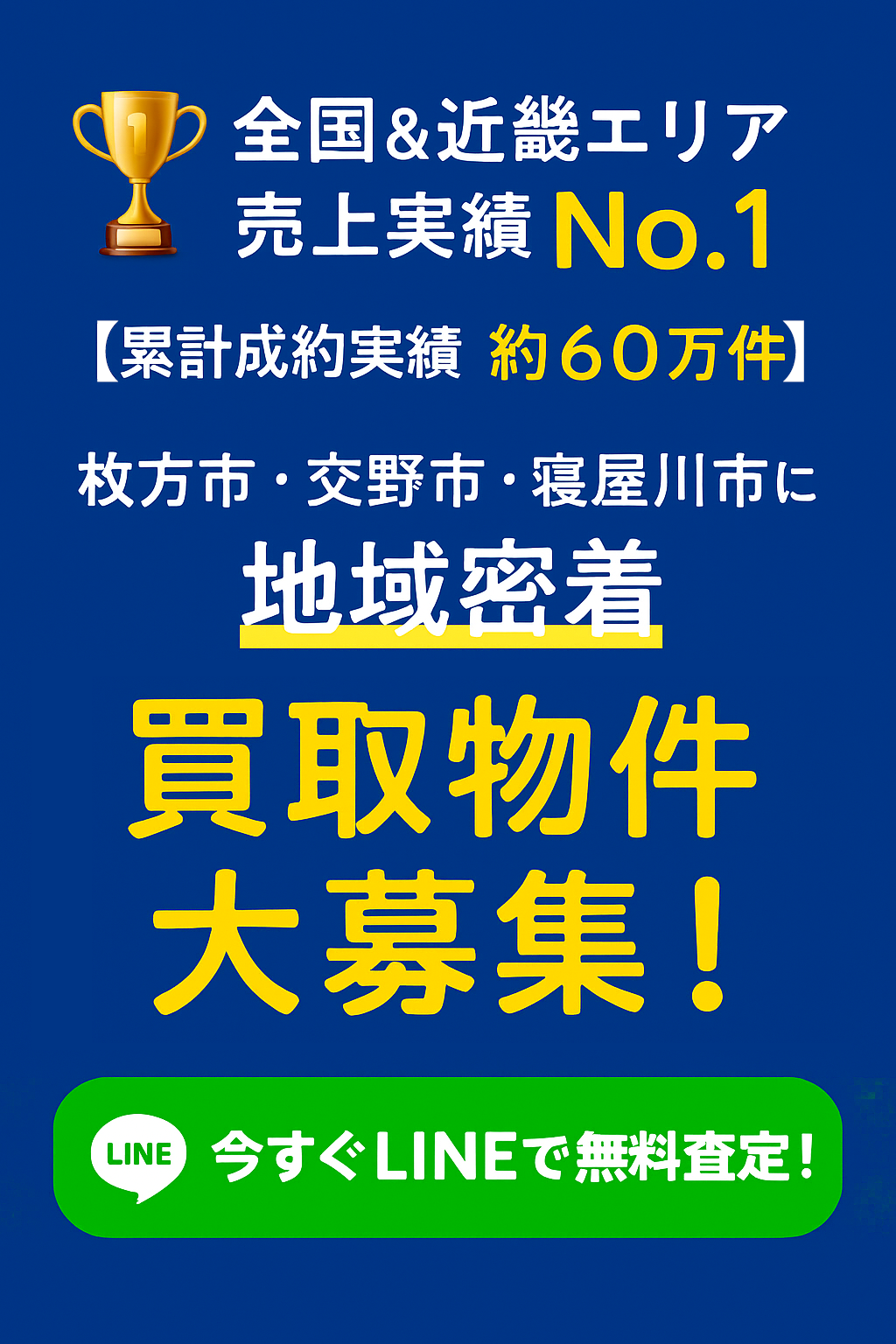こんにちは、ハウスドゥ 京阪くずは店です。
今回は「親が残した不動産をどうするべきか?」というテーマで解説していきます。実はこのご相談、枚方市を中心に非常に多く寄せられます。
相続した家や土地をどうするかは、誰もが直面する大きな課題です。「親の家をそのまま残しておこう」「思い出があるから手をつけにくい」と考える方もいれば、「使わないから早く処分したい」と考える方もいます。
しかし、不動産を放置しておくと「固定資産税」「管理費」「老朽化による修繕リスク」が積み重なり、子どもの世代に大きな負担となります。最悪の場合、老後資金を圧迫し「破産リスク」にまでつながる可能性があるのです。
本記事では「不動産売却」「土地活用」「相続対策」という3つの観点から、正しい判断基準をわかりやすく整理します。最後までご覧いただければ、相続不動産に悩む方が「どう行動すべきか」の道筋が見えるはずです。
第1章:親が残した不動産を放置するリスク

まずは「親が残した不動産をそのまま放置してしまうリスク」について見ていきましょう。
固定資産税・都市計画税の負担
不動産を所有している限り、固定資産税や都市計画税は毎年必ず発生します。たとえ誰も住んでいない空き家でも同じです。築古で資産価値が低い不動産でも、固定資産税評価額に基づいて税金が課されるため、年間で数万円から十数万円の支出となります。
この出費が続くと「資産を持っているのに負担だけが重い」という状態になり、子どもの世代が老後資金を削らざるを得なくなるケースも少なくありません。
老朽化による維持管理リスク
人が住んでいない家は劣化が早く進みます。雨漏り、シロアリ被害、外壁や屋根の損傷などが放置されると、修繕費用は高額になりがちです。
また、庭の草木が伸びて近隣住民から苦情が出る、倒壊の危険があると行政から指導を受けるなど、維持管理の負担も増していきます。
「特定空き家」に指定されるリスク
平成27年の「空き家対策特別措置法」により、管理が不十分な空き家は行政から「特定空き家」に指定される可能性があります。特定空き家に認定されると、固定資産税の住宅用地特例(最大6分の1に減額される制度)が解除され、税負担が一気に増加します。
さらに行政代執行によって取り壊され、その費用を請求されるリスクもあるのです。
老後資金への悪影響
こうした税金や修繕費の負担が積み重なると、子ども世代の家計に深刻な影響を与えます。「親から受け継いだ不動産だから」と残しておいた結果、毎年の維持費が老後資金を削り、最悪の場合「破産リスク」にまでつながりかねません。
つまり、不動産は「所有しているだけ」で資産になるとは限らず、場合によっては負債になってしまうことがあるのです。
第2章:不動産売却という選択肢

不動産を放置するリスクを避ける最もシンプルな方法が「売却」です。相続した不動産を売却すれば現金化でき、税金や維持管理の負担から解放されるだけでなく、相続人同士で公平に分けることも可能です。
不動産売却のメリット
- 現金化できる:まとまった資金として手元に残せるため、教育資金・老後資金・介護費用などに活用可能。
- 公平に分けやすい:相続人が複数いる場合も、売却代金を分配することでトラブルを回避できる。
- 維持管理の負担から解放:空き家管理や固定資産税の支払いが不要になる。
築古でも売却できる可能性
「古い家だから売れないのでは?」というご相談をよくいただきますが、実際には築古住宅でも「現状渡し」や「不動産会社による買取」で売れるケースは多いです。
特に近年では、リフォーム需要や建て替え需要が高まり「古い家付きの土地」を求める買主も存在します。また、不動産会社の直接買取であれば「残置物あり」「老朽化あり」の状態でも売却が可能です。
税制優遇:空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却する場合、一定条件を満たせば「3,000万円の特別控除」が適用されます。これは譲渡所得(=売却益)から3,000万円を差し引ける制度で、多くのケースで譲渡所得税をゼロまたは大幅に軽減できます。
条件としては、相続開始時に被相続人が一人暮らしであったこと、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、耐震リフォームや解体を行ってから売却すること、などが挙げられます。
地域市場を踏まえた売却のコツ
不動産の売却価格は「市場の需要」に大きく左右されます。枚方市やその周辺では、京阪沿線の駅近物件や生活利便性の高いエリアは需要が安定しており、築古でも売れやすい傾向があります。
一方、郊外やバス便エリアの物件は需要が限定的ですが、不動産会社の買取制度を利用すれば早期売却が可能です。相続不動産を現金化する場合は、こうした地域特性を踏まえた戦略が必要です。
不動産売却を選ぶべきケース
- 相続人が複数いて公平に分けたい場合
- 維持管理や税負担から早く解放されたい場合
- 現金がすぐに必要な場合(介護・教育・老後資金など)
- 築古で活用が難しい不動産を相続した場合
売却は「不動産を資産から現金に変える手段」です。感情的に残したい気持ちがあっても、長期的な生活設計や老後資金を守るためには、冷静な判断が必要になります。
第3章:土地活用という選択肢

不動産を「売らずに残す」という選択肢の一つが、土地活用です。相続した土地や建物を活用すれば、資産を保持しながら収益を得られる可能性があります。しかし、メリットだけでなくリスクやコストも存在するため、事前にしっかりと検討することが重要です。
代表的な土地活用の方法
- 賃貸住宅経営:アパートやマンションを建てて家賃収入を得る。
- 駐車場経営:初期投資を抑えつつ安定的に収益を確保できる。
- 店舗・事業用地として貸す:長期契約が期待でき、安定収入につながる。
- 太陽光発電事業:遊休地を活かして固定価格買取制度(FIT)による収益を得る。
土地活用のメリット
- 売却せずに資産を残しつつ、安定した収益を確保できる。
- インフレに強く、長期的に収益が見込める。
- 将来的に売却する際、収益性がある物件として価値が高まりやすい。
土地活用のデメリット・リスク
- 建築費など初期投資が大きい。
- 入居者がつかない場合や空室率が高い場合、赤字経営になる可能性。
- 建物を建ててしまうと「固定資産税の軽減措置」が外れる場合がある。
- 経営には管理や修繕などの労力・コストが発生する。
枚方市エリアでの活用事例
枚方市のように人口が多く、京阪沿線の駅周辺では賃貸需要が安定しているため、アパートや戸建て賃貸の経営が現実的です。また、駅から離れた郊外では駐車場やトランクルームとしての活用が有効なケースもあります。
さらに、遊休地や農地を所有している場合は、太陽光発電を導入して収益化を図る事例も増えています。ただし、制度変更や買取価格の低下リスクもあるため、長期的な視点で判断する必要があります。
土地活用を選ぶべきケース
- 売却せずに「資産を残したい」と考えている場合
- 安定した家賃収入で老後資金を確保したい場合
- 駅周辺や需要が高いエリアの土地を相続した場合
- 遊休地を放置するより収益化したい場合
土地活用は「資産を持ち続けながら収益を生み出す方法」です。しかし、初期投資や運営管理の負担があるため、必ず収益シミュレーションを行い、リスクを踏まえて判断することが大切です。
第4章:相続・贈与の税金対策

親が残した不動産をどうするかを考える上で、避けて通れないのが「税金対策」です。不動産には相続税や贈与税といった負担があり、知らずに進めると余計な税金を払ってしまうこともあります。ここでは、相続や贈与に関わる代表的な税制について整理しておきましょう。
相続税の基礎控除
相続税には「基礎控除」という仕組みがあり、一定額までは非課税となります。基礎控除の計算式は以下のとおりです。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、相続人が子ども2人の場合は 3,000万円 + 600万円×2 = 4,200万円 が非課税となります。枚方市の戸建てやマンションの多くはこの範囲に収まるため、相続税が発生しないケースも少なくありません。
小規模宅地の特例
居住用や事業用の宅地については「小規模宅地の特例」が適用でき、土地評価額を最大80%減額できる場合があります。親が住んでいた自宅を子どもが相続するケースでは、この制度を利用することで大幅に節税できる可能性があります。
贈与を選ぶ場合の注意点
「相続を待たずに名義を子どもに変えておく」という選択もありますが、贈与には注意が必要です。贈与税は相続税より税率が高くなる傾向があり、高額な負担になることもあります。特に評価額が高い不動産をそのまま贈与すると、多額の贈与税がかかることがあります。
相続前に売るべきか?相続後に売るべきか?
不動産を売却するタイミングによっても税金の負担は変わります。
- 相続前に売る場合:親の譲渡所得として課税され、所有期間が短いと税率39%の短期譲渡になるリスクがある。
- 相続後に売る場合:「空き家の3,000万円特別控除」や「取得費加算の特例」が使える可能性があり、節税効果が期待できる。
税金対策の基本方針
- まずは不動産の評価額を把握する
- 相続税の基礎控除に収まるかどうか確認する
- 贈与を選ぶ場合は税率や費用を試算する
- 相続後の税制優遇(空き家特例など)が利用できるか検討する
税制は頻繁に改正されるため、「自分のケースではどの制度が使えるのか」を早めに確認しておくことが重要です。枚方市エリアでも、不動産の評価額や家族構成によって最適な対策は異なります。専門家に相談しながら最適な選択を進めましょう。
第5章:失敗しないための進め方

親が残した不動産の売却や活用は、一度決断してしまうと後戻りが難しいものです。特に大きな資産が動くため、「思っていたより税金が高かった」「売却額が少なくて後悔した」という失敗を防ぐためには、正しい進め方を押さえておくことが重要です。
不動産の評価額を把握する
まず最初にすべきことは「不動産の評価額を知る」ことです。評価額には複数の種類があります。
- 固定資産税評価額:市区町村が毎年決定し、固定資産税や登録免許税の計算に使われる。
- 路線価:国税庁が公表し、相続税や贈与税の計算に使われる。
- 時価(市場価格):実際に売却できる価格。不動産会社の査定で把握できる。
この3つを整理することで「売却した場合にいくら残るか」「税金がどれくらいかかるか」を正確にイメージできます。
専門家に早めに相談する
不動産は法律・税金・市場価値が複雑に絡み合う資産です。そのため、専門家に相談することが欠かせません。
- 不動産会社:売却の流れや市場価格の目安を提供。
- 税理士:相続税や贈与税の計算、節税のシミュレーションを担当。
- 司法書士:相続登記や名義変更などの手続きを代行。
これらの専門家と連携することで「どの方法が一番得か」を数字で確認できます。
家族で話し合いをしておく
親が残した不動産は、家族全員に関係する資産です。兄弟姉妹の間で意見が食い違うと、手続きが進まなくなることもあります。特に相続人が複数いる場合は「売却するのか」「誰かが住むのか」「賃貸にするのか」といった方針を事前に共有することが重要です。
計画的な不動産整理が老後資金を守る
不動産は「持っているだけでコストがかかる資産」です。固定資産税・修繕費・管理費などが積み重なると、子どもの世代の老後資金を圧迫しかねません。売却や活用の判断を先送りにするほど負担が増えるため、早めに整理することで将来のリスクを減らせます。
失敗しない進め方の流れ
- 不動産の評価額を調べる(固定資産評価額・路線価・市場価格)
- 税金や費用を試算する(相続税・贈与税・登記費用など)
- 専門家に相談し、複数の選択肢を比較する
- 家族全員で話し合い、合意形成をする
- 売却・活用・相続などの方針を決定し、計画的に実行する
こうしたステップを踏むことで「損をしない不動産整理」が実現できます。特に枚方市や周辺エリアでは、空き家問題や築古物件の増加もあり、早めに対策を取った方が安心です。
まとめ

親が残した不動産は、大切な資産である一方で「放置することが最も危険」であると言えます。固定資産税や管理費がかかり続け、老朽化によるリスクや近隣トラブルに発展すれば、子どもの生活や老後資金を大きく圧迫する可能性があります。
選択肢は大きく分けて3つ──「不動産売却」「土地活用」「相続対策」。それぞれにメリット・デメリットがあり、家族の事情や資金状況に応じて最適解は異なります。
- 売却:現金化でき、相続人で分けやすい。税制優遇(3,000万円特別控除)を活用すれば節税も可能。
- 土地活用:資産を残しながら収益を得られる。ただし初期費用や管理コストに注意が必要。
- 相続・贈与対策:相続税・贈与税の仕組みを理解し、控除や特例を活用すれば節税が可能。
重要なのは「正しい情報を集め、専門家に相談し、家族で話し合うこと」です。早めに方針を決めておくことで、子どもの世代の老後破産リスクを防ぎ、安心した未来を築くことができます。
ハウスドゥ 京阪くずは店では、枚方市を中心に「不動産売却」「土地活用」「相続対策」のトータルサポートを行っています。査定のご依頼から税務相談、相続登記まで幅広く対応可能です。まずはお気軽にご相談ください。