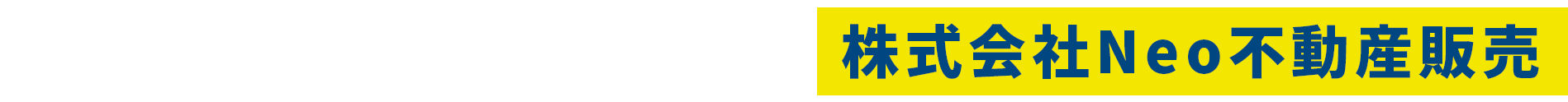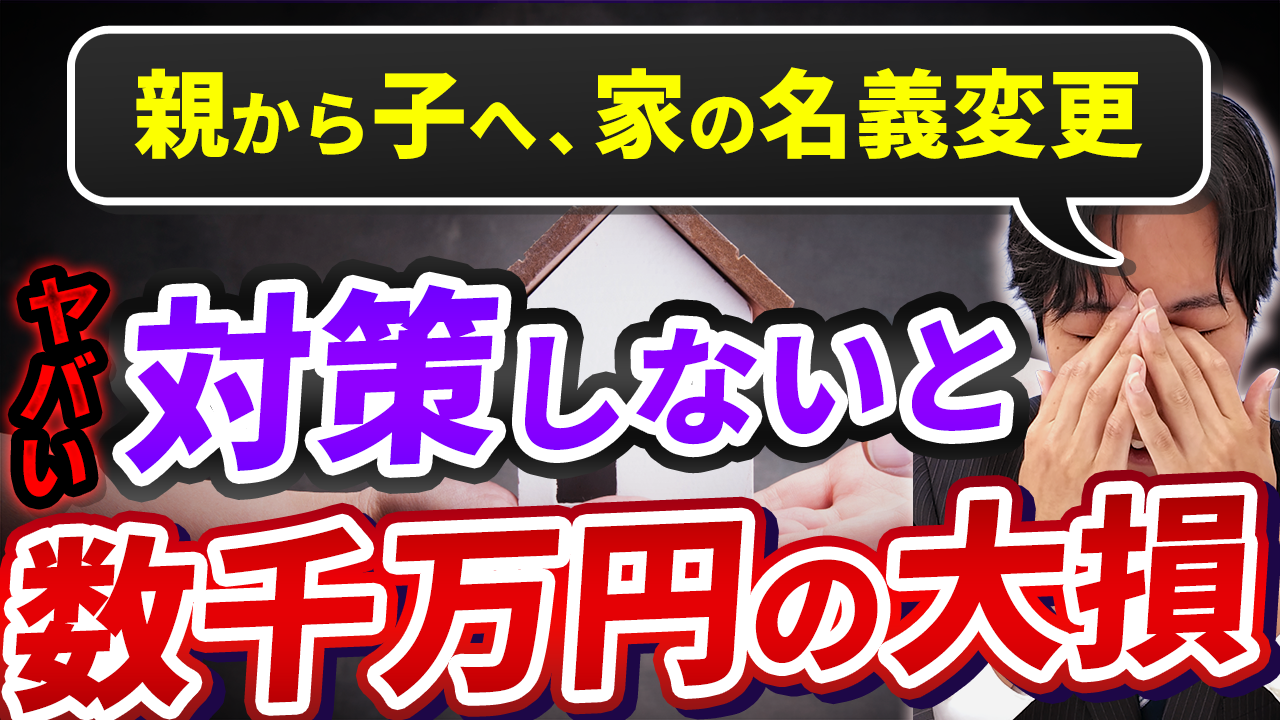親から子への名義変更にかかる贈与税と節税方法
こんにちは、ハウスドゥ 京阪くずは店です。本記事では「親から子への名義変更にかかる贈与税と節税方法」について、初めての方にもわかりやすく整理して解説します。
「親の名義を子どもに変えたいけど、どんな手続きが必要?」「贈与税ってどれくらい?」「できるだけ節税する方法は?」——枚方市をはじめ、多くのお客様から日々いただくご相談です。
家や土地の名義変更は、将来の相続を見据えた大切な準備。しかし、贈与税や登録免許税などの費用やルールを理解しないまま進めると「想定以上に税金がかかった」という失敗につながることもあります。
結論として、贈与や名義変更には明確なルールと仕組みがあります。これを理解すれば、節税の選択肢が見えてきます。最後まで読んでいただければ、「自分のケースではどう動けばよいか」が具体的にイメージできるはずです。
第1章:贈与税の基本
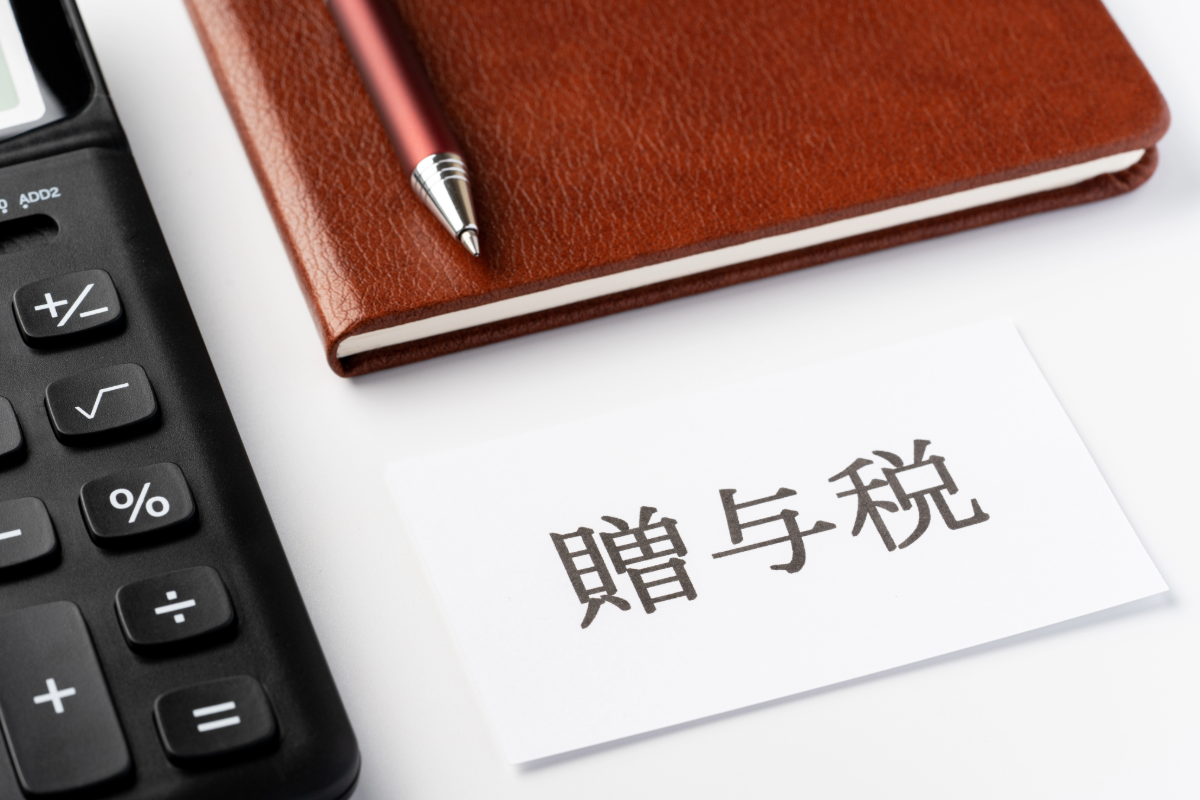
まずは、名義変更と切っても切れない「贈与税」の基本を確認しましょう。親が所有する不動産を無償で子へ移すと、一般に「贈与」に該当し、贈与税の対象になります。
贈与税とは何か
贈与税は「個人から個人へ財産を無償で移したとき」に課税される税金です。不動産(家・土地)を親から子に名義変更する行為は原則として贈与に当たり、課税対象となります。
基礎控除(年間110万円)
贈与税には毎年リセットされる基礎控除110万円があります。現金などはこの枠内であれば非課税です。ただし不動産は現物のため分割贈与が難しく、原則として評価額全体が贈与額として扱われます。
評価額がカギになる理由
贈与税の課税ベースは「時価」ではなく評価額です。例えば固定資産税評価額が1,500万円の家を贈与するなら、110万円を控除した1,390万円が課税対象額となり、ここに累進税率を適用して税額を算定します。
累進課税に注意
贈与税は累進課税で、贈与額が大きくなるほど税率も上がります。場合によっては高率帯(最大55%)に達することもあるため、事前の試算が不可欠です。
よくある誤解:「古い家=税金ゼロ」ではない
築年数が経つと建物の評価は下がる一方、土地の評価は築年とは無関係です。「古いから価値ゼロ」とはならず、土地評価が高ければ贈与税が発生し得ます。まずは「贈与税がかかる可能性がある」「税額は評価額で決まる」という基本を押さえましょう。
※税制は改正されることがあります。実行前に最新制度を必ずご確認ください。
第2章:不動産の評価額を知る

贈与税を正しく理解するためには、まず「不動産の評価額」がどう決まるのかを知ることが大切です。不動産の評価は単純に市場価格(時価)ではなく、国や自治体が定める基準に基づいて算定されます。贈与税もこの評価額をベースに計算されるため、評価方法を押さえることが節税の第一歩になります。
固定資産税評価額
固定資産税評価額は、市区町村が3年ごとに見直し、固定資産税や都市計画税の課税根拠となる金額です。この評価額は固定資産税の納税通知書に記載されており、比較的簡単に確認できます。一般的に市場価格よりも低めに設定されているのが特徴です。
路線価
土地の評価に用いられるのが「路線価」です。国税庁が毎年発表しており、道路に面する1平方メートルあたりの価格を示します。路線価に土地の面積や形状補正を掛け合わせて土地の評価額を算出します。贈与税や相続税の計算では、この路線価ベースの評価額が使われることが多いです。
評価額と市場価格の違い
評価額は市場で実際に売れる価格(時価)とは異なります。例えば、枚方市の駅近エリアで市場価格が3,000万円の土地であっても、固定資産税評価額は2,000万円程度に設定されているケースもあります。このため、贈与税の課税対象額が実際の市場価格よりも低く抑えられる可能性があります。
エリアによる評価額の差
同じ枚方市内でも、エリアによって評価額は大きく異なります。例えば樟葉駅や枚方市駅周辺のような人気エリアでは路線価も高く設定されますが、郊外の住宅街では相対的に低くなります。この差が、贈与税の金額にも直結します。
評価額を把握する重要性
贈与税は「評価額」で計算されるため、まずは自身の不動産の評価額を知ることが重要です。評価額は市役所で固定資産評価証明書を取得したり、国税庁の路線価図で調べることが可能です。あらかじめ確認しておけば、贈与にかかる税額のシミュレーションもスムーズに行えます。
第3章:贈与税が高額になるケースとリスク

贈与税は「累進課税」が採用されており、贈与額が大きくなるほど税率も上がる仕組みです。そのため、不動産のように一度に大きな金額を贈与するケースでは、想定以上に税負担が重くなることがあります。ここでは、贈与税が高額になりやすい具体的なケースと注意すべきリスクを整理します。
累進課税による負担増
贈与税は、基礎控除の110万円を超えた部分に対して課税されます。課税対象額が大きいほど税率が高くなり、最大で55%に達することもあります。例えば評価額3,000万円の不動産を贈与した場合、基礎控除を差し引いた2,890万円が課税対象となり、数百万円単位の税負担になる可能性があります。
現金での納税が必要
贈与税は不動産そのもので支払うことはできず、必ず現金で納めなければなりません。そのため、贈与を受けた側が多額の現金を用意できないと、最終的にその不動産を売却して納税資金を確保するという事態に陥るリスクもあります。
登録免許税や司法書士費用
贈与に伴う費用は贈与税だけではありません。不動産の名義変更には「登録免許税」がかかり、固定資産税評価額の2%が課税されます。さらに司法書士に登記手続きを依頼すれば、数万円〜十数万円の報酬が必要になります。これらを見落とすと予算を超える出費となる場合があります。
よくある失敗例
- 節税の特例を利用せず、一度に高額の不動産を贈与してしまい、想定外の税額が発生した。
- 贈与税の支払い資金を準備しておらず、急遽不動産を売却して現金をつくることになった。
- 登録免許税や司法書士費用を考慮しておらず、全体のコストが大きく膨らんでしまった。
注意すべきリスク
贈与は「早めに名義を移して安心」と思われがちですが、評価額や制度を理解せずに進めると逆に大きな負担を抱える可能性があります。特に評価額の高い不動産や都心・駅近の物件では、贈与税が想定以上に重くなるリスクがあるため注意が必要です。
第4章:節税方法① 特例や控除を活用

贈与税は高額になりやすいものですが、国が設けている特例や控除を活用すれば、税負担を大幅に軽減することができます。ここでは代表的な制度を紹介します。
相続時精算課税制度
「相続時精算課税制度」を利用すると、親から子への贈与について2,500万円まで非課税で贈与できます。例えば固定資産税評価額が2,000万円の不動産を子どもに贈与する場合、この制度を選択すれば贈与税はかかりません。将来相続が発生した際に、贈与した財産を相続財産に合算して精算する仕組みです。
ただし、一度選択すると毎年の贈与がすべてこの制度扱いとなり、年間110万円の基礎控除が使えなくなる点に注意が必要です。
住宅取得等資金の贈与非課税制度
子どもが住宅を購入する際に利用できる制度で、親からの資金援助について最大1,000万円まで非課税となります。新築・中古住宅の購入資金やリフォーム資金に充てる場合に適用されるため、名義変更や不動産の贈与と組み合わせて活用できるケースもあります。
教育資金や結婚・子育て資金の非課税特例
教育資金や結婚・子育て資金を目的とした贈与については、一定額まで非課税となる制度があります。こちらは対象や金額が限定されていますが、長期的な資産移転を考えるうえで有効な選択肢です。
注意点
- 特例には利用条件(住宅の床面積、築年数など)がある。
- 期限が設けられている制度も多いため、最新情報を確認する必要がある。
- メリットだけでなくデメリットもあるため、税理士など専門家への相談が推奨される。
これらの特例を正しく活用すれば、贈与税を大幅に節税することが可能です。ただし、制度を誤って利用するとかえって不利になる場合もあるため、十分な検討と専門家のサポートが不可欠です。
第5章:節税方法② 贈与のタイミングを工夫

贈与税の負担を軽くするためには、制度を活用するだけでなく「贈与のタイミング」を工夫することも重要です。同じ不動産を贈与する場合でも、タイミング次第で課税額が大きく変わることがあります。
年間110万円の基礎控除をコツコツ活用
贈与税には、年間110万円まで非課税となる「基礎控除」があります。現金を贈与する場合、毎年少しずつ贈与を行えば長期的に大きな資産を非課税で移すことが可能です。例えば10年間で毎年110万円を贈与すれば、合計1,100万円を税金ゼロで子どもに渡すことができます。
不動産評価額が下がったタイミングを狙う
不動産の評価額は、固定資産税評価額が3年ごとに見直される仕組みになっています。そのため、評価額が下がったタイミングで贈与を行えば、課税対象額が小さくなり、贈与税の負担を軽減できるケースがあります。
特に築年数の経過や市場動向により不動産価値が下がった場合は、贈与のチャンスとなります。
相続とのバランスを考える
贈与は「生前に名義を変えて将来のトラブルを防げる」というメリットがありますが、税率は相続税よりも高いため、場合によっては不利になることもあります。一方で相続には「3,000万円+600万円×法定相続人」という大きな基礎控除があります。枚方市の一般的な不動産であれば、この控除枠内で相続できるケースも多く、「贈与より相続の方が有利」になる場合もあります。
長期的な資産移転の計画を立てる
節税を考えるなら、短期的に判断するのではなく、10年・20年といった長期的な視点で資産移転の計画を立てることが大切です。毎年の基礎控除を活用しつつ、必要に応じて相続時精算課税制度や住宅取得資金の非課税制度を組み合わせれば、負担を最小限に抑えることができます。
つまり、贈与は「いつ行うか」で結果が大きく変わります。税制や評価額の変動を踏まえて、適切なタイミングを見極めることが、節税のカギといえるでしょう。
第6章:相続との比較

親から子へ不動産を引き継ぐ方法には「贈与」と「相続」の2つがあります。どちらを選ぶべきかは、ご家族の状況や資産の内容によって異なります。ここでは両者の特徴を整理し、違いを比較していきましょう。
贈与の特徴
贈与は、生前に親から子へ不動産を移転する方法です。最大のメリットは早めに名義を移せる点です。これにより、将来の相続時に名義変更の手間や相続人同士のトラブルを防ぐことができます。また、生前に子どもが自宅として利用できるため、生活の安定につながることもあります。
一方で贈与にはデメリットもあります。贈与税は相続税よりも税率が高いため、税負担が重くなりやすいのです。特に評価額の高い不動産を一度に贈与すると、数百万円単位の税金が発生するケースもあります。また、贈与に伴う登録免許税や司法書士費用も考慮しなければなりません。
相続の特徴
相続は、親が亡くなったときに自動的に財産が子どもへ移る仕組みです。大きなメリットは、相続税には基礎控除があることです。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人」の金額が非課税となります。例えば相続人が子ども2人の場合、4,200万円までは相続税がかかりません。
枚方市の一般的な戸建てや土地の評価額であれば、この範囲に収まることも多く、実際には相続税がかからないケースもあります。そのため、贈与よりも相続の方が税負担が軽く済むこともあります。
ただし、相続のデメリットとしては、名義が長期間親のままになるため、売却や担保設定がすぐにできない点があります。また、複数の相続人がいる場合は共有名義となり、不動産の活用や処分が難しくなることもあります。
どちらが有利かを判断するポイント
- 不動産の評価額が高額かどうか
- 家族構成(相続人の人数や関係性)
- 今後の相続トラブルを避けたいかどうか
- 資産をすぐに子へ移す必要があるか
例えば「早めに名義を変えておきたい」「子どもに安心して住んでほしい」という場合は贈与を選ぶことが適しています。一方で「税金をできるだけ抑えたい」「控除の範囲で済みそう」という場合は相続を待った方が得になるケースもあります。
つまり、「贈与」と「相続」はどちらか一方が常に有利というわけではなく、ご家庭の事情や資産の評価額に応じて最適な選択をすることが重要です。
第7章:名義変更の流れと必要書類

ここまでで贈与や相続の違いについて整理しましたが、実際に親から子へ不動産の名義を変更する際には、具体的な手続きが必要です。名義変更は大きく「贈与契約」「登記申請」「税務申告」の3つの流れで進められます。ここではその手順と必要書類を詳しく解説します。
名義変更の流れ
- 贈与契約書を作成
親から子へ不動産を贈与する場合、まずは「贈与契約書」を作成します。口頭でも贈与は成立しますが、登記や税務申告の際には書面が必要です。贈与する不動産の内容や日付、贈与者・受贈者の署名・押印を明記して作成します。 - 登記申請を行う
贈与契約書が整ったら、法務局に名義変更(所有権移転登記)の申請を行います。このとき「登録免許税」を納付する必要があり、目安は固定資産税評価額の2%です。 - 司法書士に依頼する場合
手続きは自分でも可能ですが、専門知識が必要で書類も多いため、多くの方は司法書士に依頼します。報酬は数万円~十数万円が相場です。特に初めての場合は、専門家に依頼した方が安心です。 - 税務申告
贈与税が発生する場合は、翌年の確定申告期間(原則として翌年2月1日〜3月15日)に税務署へ申告が必要です。申告を怠ると延滞税や加算税が課される可能性があるため注意しましょう。
名義変更に必要な書類
- 贈与契約書
- 登記申請書(法務局で入手可能)
- 固定資産評価証明書(市役所で取得)
- 贈与者(親)の印鑑証明書
- 受贈者(子)の住民票
- 両者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
注意すべきポイント
名義変更は「登記」と「税務申告」がそろって初めて完了です。登記だけを済ませて税務署への申告を忘れてしまうと、あとから追徴課税を受ける可能性もあります。また、名義変更後は固定資産税の納税義務も子どもに移りますので、負担を含めて検討しておくことが大切です。
名義変更は単なる形式的な手続きではなく、税金や将来の資産活用に直結する重要なプロセスです。スムーズに進めるためには、司法書士や税理士、不動産会社など専門家に相談するのが安心です。
第8章:注意点と失敗しないためのポイント

親から子への不動産の名義変更は、単に書類を提出して終わりというものではなく、相続や将来のトラブルにも大きく関わる重要な手続きです。ここでは、実際に多くの方が見落としやすい注意点と、失敗しないためのポイントを整理します。
注意点① 兄弟姉妹との公平性
特定の子どもにだけ不動産を贈与すると、将来の相続時に兄弟姉妹との間で不公平感が生まれることがあります。贈与された不動産の価値は「特別受益」として相続財産に持ち戻されるため、結果的に遺産分割で揉める原因になることもあります。
家族全員で話し合い、将来の相続全体を見据えた上で贈与を進めることが重要です。
注意点② 生前贈与加算のルール
贈与したからといって相続と完全に切り離せるわけではありません。相続開始前3年以内に行われた贈与は「生前贈与加算」として相続財産に戻されます。そのため「相続税対策のつもりで贈与したのに、結局加算されてしまった」というケースも珍しくありません。
注意点③ 節税だけを優先するリスク
相続時精算課税制度などの特例は便利ですが、一度選択すると年間110万円の基礎控除が使えなくなるなどのデメリットもあります。節税効果だけを優先して制度を利用すると、かえってトータルで損をしてしまう場合があるため注意が必要です。
注意点④ 手続きの複雑さ
名義変更には贈与契約書の作成、法務局への登記申請、税務署への贈与税申告など、複数の手続きが必要です。専門知識が求められるため、書類不備で手続きが滞るケースも少なくありません。結局は司法書士や税理士に依頼する方がスムーズで確実です。
失敗しないためのポイント
- 名義変更を行う前に、家族全体で十分に話し合う
- 相続と贈与を比較し、長期的に見てどちらが有利かを判断する
- 制度や特例はメリット・デメリットを理解して選ぶ
- 司法書士や税理士など専門家に相談し、事前にシミュレーションしておく
不動産の名義変更は、家族の未来に直結する大きな決断です。トラブルを避け、安心して手続きを進めるためには、冷静に準備を整え、専門家の知恵を借りることが不可欠です。
まとめ

ここまで「親から子への名義変更にかかる贈与税と節税方法」について解説してきました。ポイントを整理すると以下のとおりです。
- 贈与税は不動産の評価額に基づいて計算され、高額になることもある
- 相続時精算課税制度や住宅資金贈与の特例などを活用すれば節税が可能
- 毎年の基礎控除(110万円)や贈与のタイミングを工夫することで負担を軽減できる
- 贈与と相続にはそれぞれメリット・デメリットがあり、家族の状況に応じた選択が必要
- 名義変更は登記と税務申告の両方が必要で、専門知識や準備が不可欠
さいごに
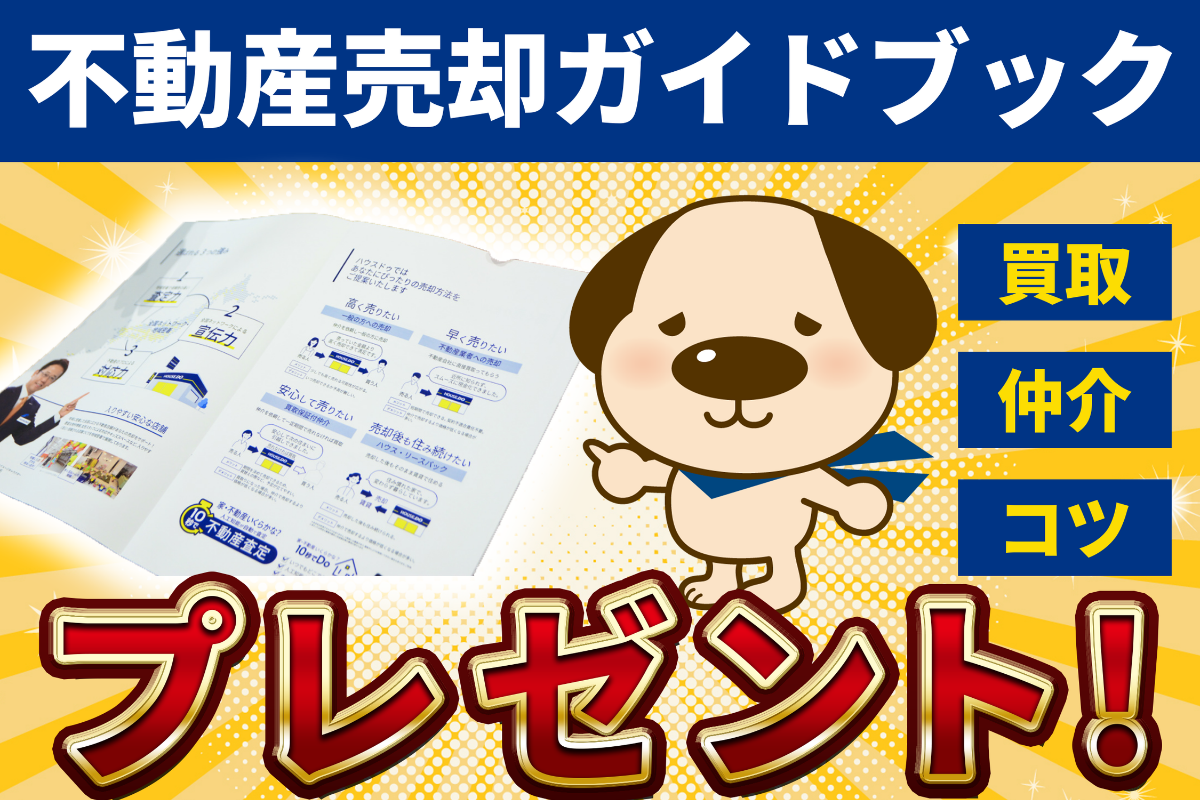
親から子への名義変更は、相続対策や将来の安心のために有効な手段ですが、税制や手続きは非常に複雑です。誤った判断をすると、想定外の税負担や家族間のトラブルにつながることもあります。
ハウスドゥ 京阪くずは店では、枚方市を中心に不動産売却や相続・名義変更のご相談を承っております。贈与税や相続税のシミュレーション、制度の比較検討、専門家との連携まで一貫してサポート可能です。
「親から子に家を贈与したい」「節税方法を知りたい」「まずは評価額を確認したい」という方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
公式LINEやホームページから24時間受付中です。
今なら『不動産売却・相続ガイドブック』を無料でプレゼントしています。